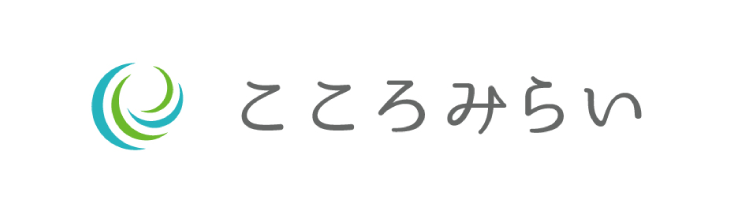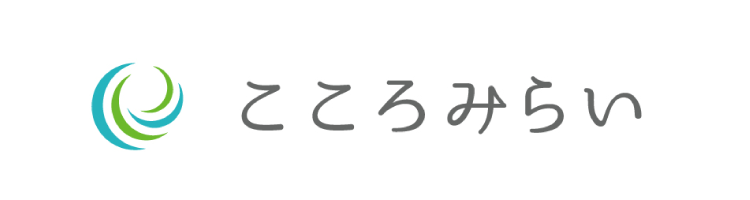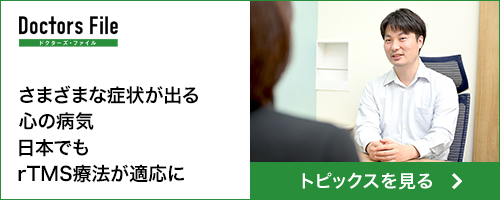自律神経失調症の治療で漢方薬を使うケース
一般的な病院やクリニックでの自律神経失調症の治療では、抗うつ剤や抗不安薬を使って症状を緩和し、落ち着いたら原因のストレスなどに向き合っていくことが多いです。
しかしながら、状態によっては漢方薬が活躍してくれることもあります。主に以下のようなケースで様々な漢方薬が使われています。
- お薬に対する抵抗が強い場合
- 妊娠および授乳している場合
- 不定愁訴がみられる場合
- お薬による副作用がみられる場合
①お薬に対する抵抗が強い場合
自律神経失調症の治療では、患者さんの状態を総合的に考えて、抗うつ剤や抗不安薬を使っていくことが多いです。最近の抗うつ剤は安全性も高く、適切に使っていれば身体への負担も大きくはありません。状態が落ち着いてくれば、少しずつ減らしながらお薬を中止していくことができます。
しかしながら、「お薬は飲みたくない」という患者さんは少なからずいらっしゃいます。
そのような場合は、患者さんが納得してくれていないまま無理にお薬を処方はしません。「どうしてもお薬は嫌だ」という方に対しては、まずは漢方薬での治療を提案することもあります。
漢方薬で効果がみられることもあります。漢方薬はプラセボ効果(薬を飲んだ安心感による心理的効果)も大きいと言われていますので、本来の漢方薬の効果以上にしっかりと効くこともあります。
ただし、その効果は個人差がとても大きいものです。効果が不十分な状態で飲み続けていても、自律神経失調症の改善はなかなか難しいため、その場合はお薬を使っていくことも必要になります。
②妊娠している場合
自律神経失調症によく使われるSSRIなどの新しいタイプの抗うつ剤は、パキシルを除き奇形率を高める等の報告はなく、妊娠中も継続して飲むことは可能です。
しかしながら、やはり不安で飲みたくないという患者さんもいらっしゃいます。
漢方薬も妊婦さんに対する絶対の安全性が確認されているわけではないのですが、効果がマイルドなものなら安全性は高いと考えられていますし、漢方の方が安心できるという患者さんの場合には漢方に切り替えることもあります。(※妊娠中は飲めない漢方薬もありますので、服用の際は医師や薬剤師さんに相談してください)
※抗うつ剤の妊娠への安全性については、『抗うつ剤の妊娠への影響とは?』をお読みください。
③不定愁訴がみられる場合
漢方薬は、身体の全体的なバランスの崩れを整えていくことで効果を発揮します。このため、ピンポイントの症状というよりは、いわゆる不定愁訴(原因のはっきりしない漠然とした不調)には強みがあります。
抗うつ剤や抗不安薬である程度の改善がみられるようになっても、全体的に何となくスッキリしない症状が続くときなどに漢方薬を追加することで、その効果の補助が期待できます。
例えば、不安の症状がお薬で落ち着いた後、「どうにも気力がでない」「何かをしたいという気持ちがおこらない」という場合があります。このような時には、補気剤として補中益気湯や十全大補湯、人参養栄湯などを用いると良くなることがあります。
それ以外にも、身体のさまざまな症状に対して漢方が効果を発揮するケースがあります。抗うつ剤の効果を補うためによく使う漢方薬には以下のようなものがあります。
| 症状 |
漢方薬 |
| 喉頭部の違和感 |
半夏厚朴湯などの気剤 |
| 意欲低下 |
補中益気湯・十全大補湯など |
| 頭痛 |
呉茱萸湯・釣藤散など |
| 肩こり |
葛根湯など |
| めまい |
苓桂朮甘湯・真武湯など |
| 腹痛 |
大建中湯・桂枝加芍薬湯など |
| むくみ |
五苓散・防己黄耆湯など |
④お薬による副作用がみられる場合
抗うつ剤をはじめとした精神科のお薬では、さまざまな副作用が認められることがあります。その際には減薬するのが基本ですが、効果がしっかり出ている時は減らせないこともあります。そのような時に、漢方薬で副作用の軽減を試みたりもします。
ただし、漢方薬は患者さんそれぞれの体質など「証」に合わせて処方することが重要なため、それが合っている場合に使っていきます。副作用を改善させるために使う漢方薬には、以下のようなものがあります。
| 副作用 |
漢方薬 |
| 口のかわき |
白虎加人参湯・麦門冬湯・五苓散・猪苓湯など |
| 便秘 |
大黄甘草湯・麻子仁丸・防風通聖散など |
| 下痢・嘔吐・胃もたれ |
五苓散・六君子湯など |
| めまい・ふらつき |
苓桂朮甘湯・真武湯・半夏白朮天麻湯など |
| むくみ |
五苓散・防己黄耆湯など |
| 排尿障害 |
八味地黄丸・牛車腎気丸など |
| 性機能障害 |
八味地黄丸・補中益気湯など |
| 高プロラクチン血症 |
芍薬甘草湯など |
| 肝機能障害 |
小柴胡湯・柴胡桂枝湯など |
※漢方薬を選ぶ時の「証」について知りたい方は、『漢方の「証」について』をお読みください。