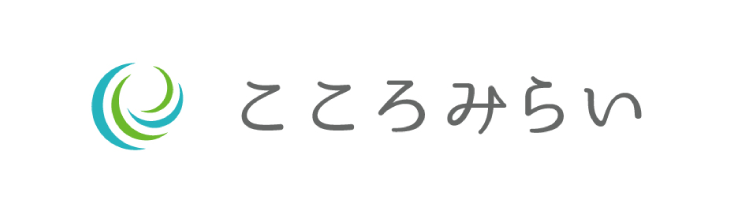適応障害の症状・診断・治療
適応障害とは?

適応障害とは「環境の変化に適応できず、そのストレスによって心身に何らかの症状がおき、生活に支障がでる病気」です。
環境が大きく変化したときには誰にでも起こり得る身近なもので、有病率は5~20%とも言われています。環境の変化を些細なものと感じていても、その人の性質に上手く折り合わなければ強いストレスがかかり、適応障害を発症してしまうことがあります。
それは決して、本人の弱さだけが問題ではありません。
例えば、バリバリ仕事ができる人であっても、どうしても合わない人間関係があれば、そこから適応障害につながってしまうこともあります。この例に限らず、職場や家庭などの日常で、様々な変化にさらされ、適応していくことが求められます。
しかし、何とか適応しようと努力しても、それが上手くいかないと、そのギャップがストレスとなります。ストレスが心身に症状をきたすようになると、適応障害として治療が必要になっていきます。
そのストレスがあまりに続いてしまうと、うつ病などにも発展していくことがあります。
適応障害について簡潔に知りたい方は、以下をお読みください。
適応障害の症状

適応障害によって心身におこる症状には様々なものがあります。一言でいえば、『ストレスで生じる症状すべて』になります。
【適応障害でおこる症状の例】
- 心の変調
不眠、不安、気分の落ち込み、イライラなど - 体の変調
胸のドキドキ、吐き気、便秘、めまい、ふるえなど - 能力の低下
仕事や作業に集中できない、考えにまとまりがなくなる、ぼーっとしてしまう、もの忘れがひどくなるなど - 行動の障害
お酒が増える、タバコが多くなる、口論がふえるなど
ストレスによって落ちこむ人もいれば、不安が強くなる人もいます。イライラしてケンカや口論が増えてしまったり、お酒やタバコの量が増えてしまうこともあります。
これらの症状は、そのストレスに反応して生じたもので、それそのものに特別な意味はありません。「適応できない環境にあること」が原因であって、ストレスとなっている環境から離れることができると症状は軽快していきます。
もしストレスのある環境から離れても症状が良くならない場合、本質的には異なる問題が隠れていることが少なくありません。
適応障害をチェックする診断基準
心の病気は、検査などによって明確な診断することが難しい領域です。もちろん、これでは診断に偏りがでてしまうので、国際的な診断基準を参考に診察・治療を進めていきます。
これらの診断基準の要点は、以下の4つの項目です。
- ハッキリとしたストレスの原因があって、3か月以内に症状が出現
- 著しい苦痛や生活に支障がある
- ほかの精神疾患でも、死別反応でもない
- 原因となるストレスを除去すると、6カ月以内に症状の改善が見られる
このように、適応障害は『明確な原因』があって、それがストレスになることが診断の前提です。
そのため、「原因はよくわからない・・・」という方は、適応障害とは診断できません。
また、上手く適応できないという経験は、誰でも思い当たることがあることですが、症状や悩みが生活に支障があるレベルでなくては適応障害になりません。
そして、他の精神疾患ではないことも診断基準の一つです。
また、死別反応は適応障害とは分けて考えます。これは、親しい方が亡くしてしまったあとは誰しもが苦しみをうけますので、そういった状況は切り分けて診断を進めて行きます。
そして、ストレスの原因がなくなれば、適応障害では比較的すみやかによくなっていくことが予想されます。
こういった特徴をもつ場合、適応障害と診断します。
適応障害とうつ病の違い
適応障害と症状が似た病気でうつ病があります。
では、この2つの病気はどのような違いがあるのでしょうか?
先ほど、適応障害の診断基準のところで「他の精神疾患である場合は診断しない」と述べました。
そのため、うつ病と診断される場合は、うつ病が優先されるということになります。
うつ病は、「一定レベル以上の気分の落ち込みがあること」で診断されます。
つまり、診断基準に基づくと、適応障害はストレスの原因から、うつ病は症状の程度から診断されてるのです。
実際には、適応障害かうつ病かどうかは、原因や症状の経過から判断していくことが多いです。
適応障害
- 環境変化によるストレスと明かな因果関係がある
- ストレスがなくなれば、症状もよくなる
うつ病
- ストレスが持続的にかかって、少しずつ悪化していく
- ストレスがなくなっても、すぐに良くならないことが多い
という特徴があります。
このような特徴の違いは、それぞれの病気の本質的な違いがあらわれています。
- 適応障害・・・
本人と環境のギャップが原因という、心理的な要因が大きな心因性の病気 - うつ病・・・
ストレスの蓄積の結果、脳の機能的な異常が大きな要因となっている内因性の病気
国際的な診断基準が作られる前の古典的な考え方ですが、心因性か内因性かという考え方は、治療に当たっては非常に重要です。うつ病のような、機能的な問題であれば、お薬を使ってしっかりと治療していく必要があります。
このように、本質的な原因を考えたときに、たとえ環境変化が原因であっても脳機能の低下が認められる場合は、うつ病と診断することもあります。
診断例)
- 月の残業100時間越えのような状況
- 2ヶ月して調子を崩してクリニック受診
- うつ病一歩手前の状態
- 脳の機能的な異常が生じている可能性が認められてる
このような場合、「抑うつ状態」や「小うつ病(minor depression)」などと診断することもあります。
適応障害は誤解を招きやすい病気
適応障害は、誤解されやすい病気です。
- 良いことがあったのにどうして調子が悪くなるのか?
- 本人の甘えではないか?
- 今後もメンタル不調をきたすのではないか?
こういったことを周囲から思われがちだからです。しかし、生活に支障をきたすほどの不調はしっかりと治療していくことが必要です。
良いこともストレスになりうる
適応障害は、けっして悪いことばかりが原因ではありません。
「環境の変化と自分の価値観とのギャップ」が原因となります。
例えば、結婚や出産、進学や昇進など、本人が望んでいたことだとしても、その変化に自分がついていけなければ、大きなストレスとなってのしかかってきます。
ですから、周囲から喜ばしいことでも、たとえ自分が望んでいたことでも、適応障害を発症することがあります。
適応障害は甘え?
また、適応障害は、本人の甘えというように解釈されてしまうこともあります。「環境変化なんて誰でもあるものだから・・・」「その程度のストレスで病気になるなんて・・・」といった印象を持たれがちです。
本人もそのように悲観的に捉え、自分を責めてしまっている方も少なくありません。しかし、患者さん自身におこっている自律神経の異常による症状は、「気のせい」や「甘え」ではなく、「現実の変調」です。
周りから見たら些細な変化であっても、どうしても折り合いがつかないことは誰しもが持っています。個人が感じる強いストレスが自律神経のコントロールを失せ、実際につらい症状がおきているのです。ですから、誰でも適応障害になる可能性があるのです。
今後もメンタル不調になるのでは?
適応障害は本来であれば、繰り返す病気ではありません。
ここまでお話しした通り、適応障害は『原因となるストレスを除去すると、回復する病気』だからです。適応障害が一度治ったということは、原因となっていたストレスも一度除去されているはずです。
もし、適応障害の再発してしまった場合は以下のことが考えられます。
- 一度は脱却したものの、前回と同じストレス環境に陥ってしまった。
どちらも、やはり明確なストレスの原因があります。そのため、適応障害から回復した後は、同じ環境に陥らないように注意し、ご自身の適応能力を少しずつ上げていくことで再発の予防が可能です。
ストレスの原因は人それぞれ
適応障害の発症には、様々な要因が関わります。
単純に環境の変化だけではなく、ちょうど体調に異変がおこりやすい年齢であったり、季節的に不安定になりやすい時期だったり、色々なことが重なり、必要以上にストレスを強く受けてしまっているケースが多いものです。
--例えば、引っ越しで体調を崩したら「たかがそれぐらいで…」と周囲は思うかもしれません。
しかし、花粉に弱い体質の人が春に山の近くに行けば、普通の人では考えられないくらいのダメージを受けますね。
言ってみれば、適応障害も同じような状態です。ある人にはなんてことのない環境が、ある人にとっては強いストレス要因となってしまうことはめずらしいことではなく、心身のバランスが崩れがちな時期に自分の苦手な状況がおこれば、普段はストレスに強い人であっても適応障害にかかる可能性は十分にあり得るのです。
大切なことは、「ストレスに対し、自分が適応できなかった原因は何か?」を理解し、糧としていくことです。
当院での適応障害の治療
当院の適応障害の治療は以下の流れを軸としています。
- ストレスの原因の発見
- 現状に対する改善方法の模索
- 本人の適応能力向上
適応障害の場合、その原因となっている環境が明確なため、その環境から離れることができれば症状は軽快していきます。しかし、離れることが難しいからこそ悩んでいる人が多いわけで、話はそう単純ではありません。
環境の変化というのは、人生において避けては通れないものです。
例えば、現在の仕事が大きなストレスになって心身に変調がおこっているとして、その仕事を離れればとりあえずは元気になれるかもしれませんが、今度は転属や転職という新たなストレス要因が待っています。
適応障害は、「自分と環境のギャップが大きくて強いストレスがかかっている状態」です。
まずは客観的に整理をしなくては、自分にとって適切な環境を選んだり、ストレスに対処したりすることは難しいと言えます。
そのため、適応障害の治療は、医師とともに現状を客観視し、問題を整理して解決策に1つずつ取り組んでいきます。
それを自分の力だけで行うのはとても大変なことです。不眠や不安が病的に強くなってしまっている状態では、冷静な判断をすることもできません。そういうときは薬の力を借り、少し落ち着きを取り戻すことも有効な手段となります。
適応障害での薬の役割
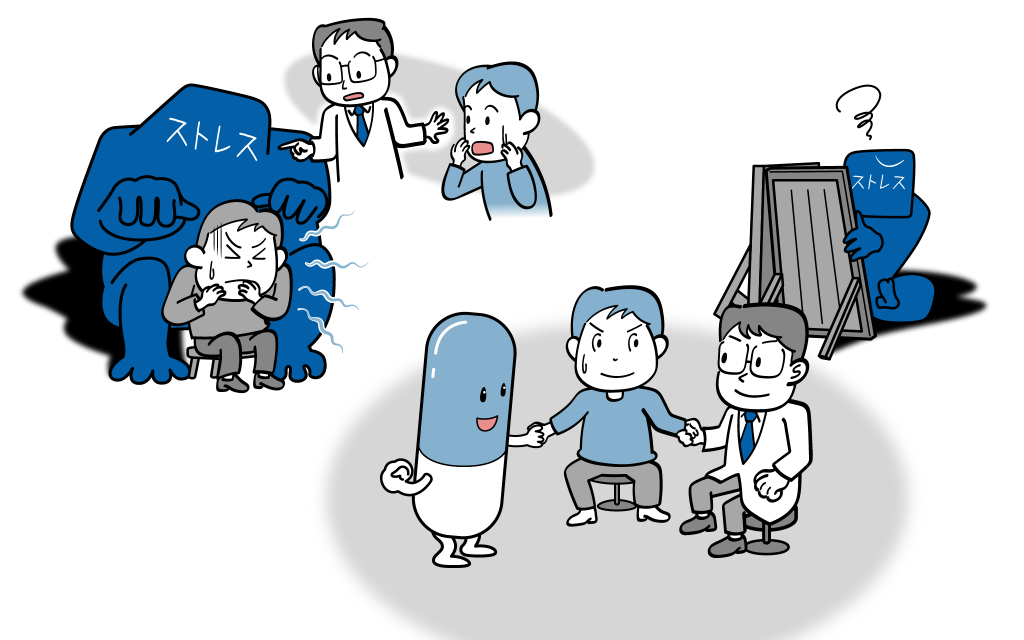
心身の状態が深刻に追いつめられているとき、薬を使って症状をやわらげることは、治療のためには有効な手段の1つです。
しかし、そのときにおこっている苦痛な症状をやわらげるものとして処方していくため、それが適応障害の根本的な治療になるわけではありません。
適応障害は、自分と環境との折り合い方法を探し、実際に行動していくことが治療の柱となり、薬はそのための助けとして使います。
心身が楽になると、物事のとらえ方が変わり、現実的な問題に問題に向き合いやすくなり、結果として解決につながっていくこともあります。
薬に対して不安に思われる方も少なくありませんが、適切に使用すればメリットは大きいです。
むやみに依存してしまうものでもなく、副作用も一時的なものがほとんどです。
適応障害では、一時的に症状を落ち着けるために使われることが多く、落ち着いてきたらお薬を減らしていくこともできます。
適応障害で使われるお薬とは?
適応障害では、困っている症状を軽減するためのお薬を使っていきます。
咳が出たら咳止め、頭痛がするならば痛み止めといった風邪の時のように、症状に合わせて処方されます。
ここでは、どのようなお薬が良く処方されるのか、ご紹介したいと思います。
不安や緊張が強いとき
- 抗不安薬
メイラックス、ワイパックス、ソラナックス、レキソタン、デパス、リボトリール、リーゼ、セディールなど
いわゆる精神安定剤などといわれているお薬です。
1日効果を持続させた方が良い場合は、メイラックスなどが使われることが多いです。筋肉の緊張が強い場合は、デパスやレキソタン、リボトリールなどが使われることが多いです。
詳しくは、抗不安薬(精神安定薬)のページをお読みください。
抑うつが強いとき
- 抗うつ剤
ドグマチール、ジェイゾロフト、レクサプロなど
一時的なサポートでよい場合は、ドグマチールが良く使われます。もともとは胃薬として作られたお薬になります。
以下のような場合、ジェイゾロフトやレクサプロといった抗うつ剤を長期的に使われることもあります。
- うつ状態が深い場合
- 環境が変えられず、症状が続くことが予想される場合
- 不安障害などが背景に認められる場合
詳しくは、抗うつ剤のページをお読みください。
不眠がみられるとき
- 睡眠薬
マイスリ―、アモバン、レンドルミン、ベルソムラなど
睡眠薬は様々な種類が発売されています。不眠の状態に適したお薬が使われます。
詳しくは、睡眠薬のページをお読みください。
イライラが強いとき
- 漢方薬
抑肝散など - 気分安定薬
デパケンなど - 抗精神病薬
ルーラン、ジプレキサ、セロクエル、リスパダールなど
興奮を抑える抑肝散といった漢方薬や、気分安定薬に分類されるデパケンなどが使われます。
適応障害で休職すべき?
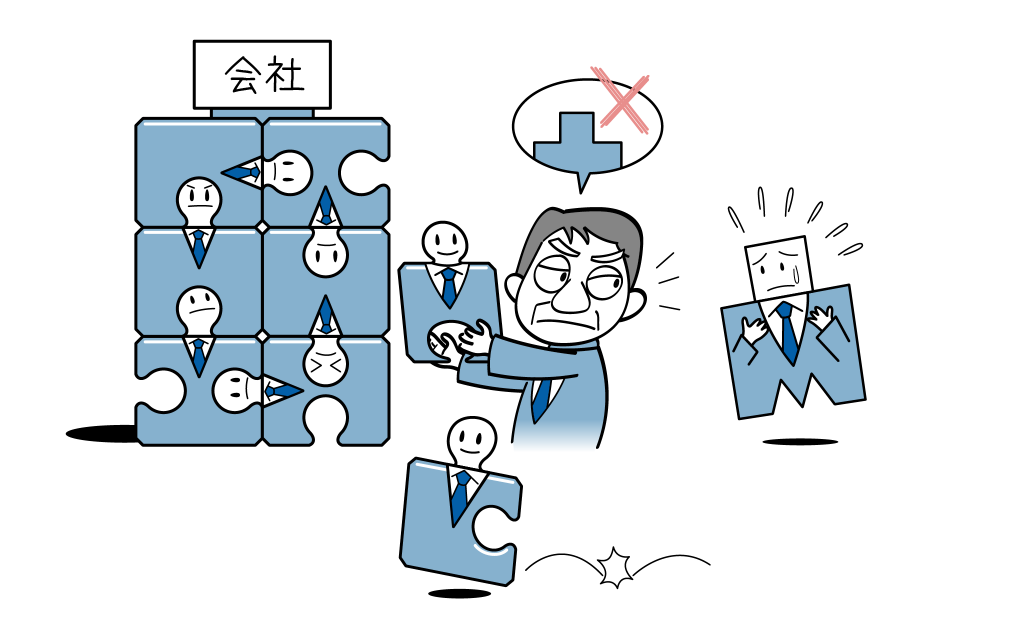
ストレスの原因が仕事にあるとはっきりわかっているなら、仕事を休んだ方がいいかどうか悩む人も多いと思います。
ですが、適応障害の場合、その環境を避けるだけでは根本の解決にならず、仕事を休んだことでかえって復職が難しくなったり、周囲との関係がギクシャクしてしまったりするケースもあるので、慎重な判断が大切です。
職場で環境調整のご相談をしていく場合は、以下のようなステップがあります。
- 上長に相談する
- 人事や総務などの相談窓口を利用する
- 産業医に相談する
- 病院で診断書をもらう
どのような方法が適切なのか、それは患者さんごとに異なります。患者さん本人だけでは難しいですので、医師と相談の上、病気の状態や職場環境などを十分に考慮し、検討することが望ましいです。
こころの病気については、昔に比べればずっと社会的認知度も上がってきているとはいえ、十分な理解を受けていると言えるほどの状況ではなく、体の病気と比べると職場や周囲への対応は難しい部分もあります。
患者さんそれぞれの病状・職場環境・生活状況などで、臨機応変に対処することが大切となります。
つらいときには1人で悩まず、病院で相談を
適応障害の患者さんには、「この程度で病気だなんて弱音を吐いたらいけない」と我慢してしまっている人も多く見られます。周囲に相談しても、「そんなの慣れたら大丈夫」「みんな通る道だから」などと励まされてしまい、よけいに落ち込んだということはありませんか?
適応障害も含めこころの病気は、経験が無い人にはなかなか理解が難しいものです。だからこそ、そのようなときは医療機関に相談してください。
ストレスは、1人で我慢して抱え込んでしまうと、よけいにふくらんで悪循環になります。診察の中で病状をお話しになり、現在の状況が客観的に整理されるだけで、気持ちが軽くなったとおっしゃる患者さんも少なくありません。
そのまま放置していると、うつ病や不安障害などを発症してしまう恐れもあります。一方で環境から離れれば楽になれると、突発的に仕事を辞めてしまったりすると、後悔をすることになるかもしれません。
心身が辛いときには、1人で重大な決心をしない方がいいものです。冷静さを取り戻せれば、いい方法が見えてくることがあります。
また、職場やご家族に対してどのように接していくかも、適応障害の治療では大切です。医師と相談しながら対処を考えていきましょう。
こころの病気というと何か特別もののように感じるかもしれませんが、適応障害は、ごく普通に生活をしている人がかかる病気です。誰にでも可能性のある病気なのです。
治療の中で環境との折り合いが上手くつけられるようになれば、適応障害は改善していきます。悩んでいるときは1人で抱え込まず、医療機関へ相談してください。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。
カテゴリー:適応障害 投稿日:2024年7月12日