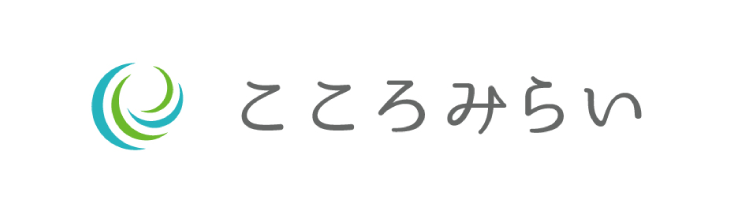気分変調症は性格の問題?心の病気?
気分変調症と性格
気分変調症は、慢性的に何だか気持ちがすっきりせず、上手くいかない思いを抱えている病気です。そんな中で何とか日々の生活を過ごしている中で、「性格」と思い込んでしまう方も多いです。
そもそも性格とはいったいなんでしょうか?人には生まれもっての気質がありますが、成長の過程で少しずつ性格がつくられていきます。性格は変えられない・・・そんな思いを抱えて生きている方は多いと思います。
気分変調症は、薬ですぐに治せる病気ではありません。ですが、薬のサポートも踏まえながら自分自身を見つめていくと、少しずつ苦しみがうすれていきます。ここでは、気分変調症と性格について考えていきたいと思います。
性格とは?
私たちは、いろいろな状況にあわせて、行動や態度をとります。その背景には、その人それぞれの一貫した思考と感情のパターンがあります。このように、その人を特徴づけているような持続的で一貫した行動パターンを性格といいます。
性格にはうまれつきの「気質」といわれている部分に、環境や経験が積み重なって「性格」になります。その上に、社会の中で作られた「社会的性格」、社会の中での役割の中で作られる「役割性格」があります。
社会的性格とは、日本人ならば・・・男ならば・・・女ならば・・・といった性格です。役割性格とは、お母さんなら・・・お父さんなら・・・高校生なら・・・といった性格です。
気分変調症は性格なのか?
若くしてこの病気を発症する人は、思春期に特有の感情だと思い込み、とくに問題視することなく放置することも多いです。なんとなく憂うつな気分を抱えたまま年齢を重ねていきます。このため、家族や友人たちも本人の性格によるものだと誤解してしまいます。
気分変調症の方は、いろいろな経過をとられています。辛い環境や経験が重なって気分変調が進んでいく方もいます。一方で、少しずつ気分変調が進んでいく中で、うまくいかないことが積み重なっていくような方もいます。
このように、はっきりした要因がなくても気分変調症につながる方は確かにいらっしゃるので、気分変調症を完全に性格であるとは言えないかと思います。確かに、つらい経験が重なることで性格傾向にも影響を与えることはあるかと思います。
特に思春期の性格形成の期間では、環境要因が強く影響してしまいます。ですが、それは後からできたものですので、修正していくことはできると考えています。
気分変調症と性格は変えられる?
気分変調症の方は、気分を整えてあげることで物事のとらえ方が少しずつ変わっていきます。気分が落ち込んでいるときは、色々なことをマイナスにとらえてしまいます。ですが、気持ちが落ち着くと客観的にとらえられるようになっていきます。
ただ、長年にわたって苦しんでいる方が多く、その経験は性格にも影響を及ぼしていることがあります。それでは、性格はかえられるのでしょうか?性格は後から作られたものほど変えられます。つまり、役割性格>社会的性格>性格>気質の順に変えやすいです。
気分変調症の患者さんの中では、家庭では良いお母さんで、ママ友付き合いはうまくやっている、けれど心の中につらさを抱え続けているような方もいらっしゃいます。役割性格や社会的性格はなんとか変えられるのです。さらに中核の「性格」も時間をかけて向き合っていくことで、少なくとも本人を苦しめるような考え方を和らげていくことはできます。
気分変調症では薬のサポートも含めて気分を整えながら、少しずつ性格と感じるまでに固まってしまった部分をほぐしていくことで、少しずつ生きやすくなっていく病気です。
気分変調症の頻度
気分変調症は、きっかけとなる出来事が曖昧であることから、発見自体が難しく、正確な発病率を出すことはできていないのが現状です。ですが人口の約6%が、一生のうちに一度は発症するといわれます。本人も周囲の人間も病気であることに気づかず、気分が沈みやすい「性格」とみなしている人も多く、実際はこの数字以上に存在していると思われます。
年齢層としては20~35歳、そのなかでも未婚者や低所得者に多く見られます。このことは、環境が発症に関係が大きいことを示唆しています。男女別に見ると、男性に比べて女性の方が、発症する可能性が2~3倍高くなっています。
まとめ
性格とは、うまれつきの気質から、環境や経験が重なって形成されていきます。
気分変調症は、気分が変調している病気です。さらに長く苦しむことで、性格に影響を与えていると考えています。
気分変調症では薬のサポートも含めて気分を整えながら、少しずつ性格と感じるまでに固まってしまった部分をほぐしていくことで、少しずつ生きやすくなっていく病気です。
気分変調症は、6%の方が一生のうちに発症するともいわれています。女性の方が多いです。
【お読みいただいた方へ】
医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。
「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。
医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(医療経験を問わない総合職)も随時募集しています。
(医)こころみ採用HP取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。
カテゴリー:うつ病 投稿日:2023年3月23日