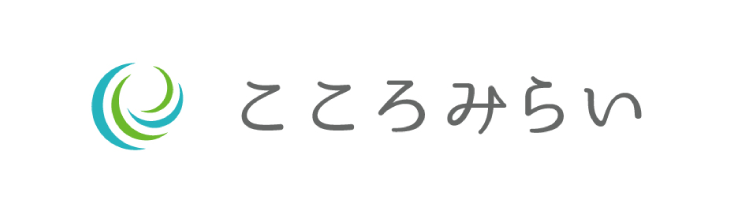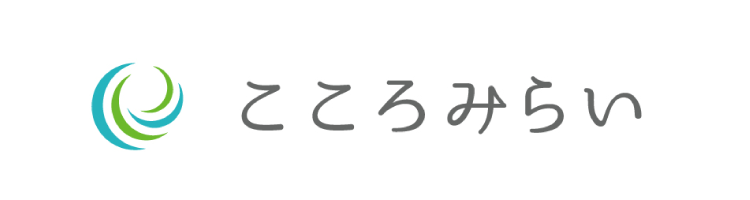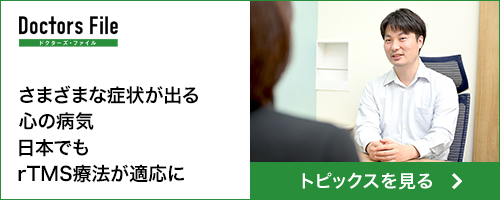認知症で見られる妄想の理由
物盗られ妄想の場合、失くしたものをどこに置いたかという記憶は喪失しています。
その際に認知症の症状に対する苦痛、介護生活への不満などが影響して、自分のものを盗られたと思い込むことがあります。
思い込みが強くなると、盗られたことに対してさまざまな理由を付け足し、物語を正当化するのです。
いくら説明しても聞き入れず、ますます話がこじれてきます。これが物盗られ妄想の生じる理由です。
徘徊の理由
徘徊がみられる際には、外出した理由を忘れて、行く先が分からず歩き回っているのかもしれません。
また現在の居場所が分からず、不安感が強くなり、安心できる場所を探しているのかもしれません。
さらに自宅にいるのに「家へ帰る」というのは、子どもの頃に住んでいた家を思い出しているのかもしれません。
それを「ここが自宅だ」と説明しても理解できませんし、よけいに不安が増すだけです。
認知症で見られる怒り・妄想・徘徊を落ち着かせる方法
認知症の方に怒り・妄想・徘徊が見られるときの対処法を解説します。
プライドを傷つけない
認知症のためにできなくなったことをできるまでさせようとしたり、忘れたことを思い出させようとしたりすると、相手のプライドを傷つけてしまいます。
できなくなったり、忘れたりするのは認知症のせいであり、そのまま受け入れるしかありません。
たとえば自宅にいるのに「家に帰る」という場合、まず本人の言うことに共感してください。そのうえで「お茶でも飲んでから帰りませんか」というふうに対応するとよいでしょう。
意見や行動を一方的に否定しない
認知症になると言っていることが矛盾していたり、行動が間違っていたりすることが多くなります。
それを正そうとしても解決せず、認知症の方の怒り・不安が強くなり、事態がこじれてしまいます。
認知症の方の意見や行動を一方的に否定せず、受容するように心がけてください。
たとえば盗られ妄想で「誰も盗っていない」と説き伏せても意味がありません。共感したうえで一緒に失くしたものを探すと落ち着くことがあります。
怒りや不安の理由は聞かない
認知症の方は、自分の怒り・不安の理由も認知できないことが多いようです。怒っている理由を尋ねられても答えられません。
理由を聞く代わりに、相手の言うことをおうむ返しにするのがよい方法です。
たとえば「だまされた」と言えば「だまされたの?」と答えるといった具合です。こういったやり取りをしているうちに、自然と怒りがおさまってくることがあります。
落ち着くまで距離をおく
怒りが高まり、暴言・暴力につながりそうな場合、その場を離れて落ち着くまで待つほうがよいでしょう。
そうすると自然におさまってくるものです。興奮状態のときにやたら対応すると、かえって症状が強くなります。
スキンシップでメッセージを伝える
認知症が進むと言葉でメッセージを伝えるのが難しくなります。代わりにスキンシップでメッセージを伝えるとよいでしょう。
手を握る、そっと背中をさするといった触れ合いで安心感を伝えてください。
ただし、いきなり手を握ると怖がらせるので、離れた場所から少しずつ距離を縮め、相手の表情を見ながらスキンシップをとるのが秘訣です。
まとめ
認知症になると怒り・妄想・徘徊といった症状がみられ、対応が困難になることがあります。
それぞれの症状が生じる理由を理解し、認知症の方のプライドを傷つけない、意見や行動を一方的に否定しないといった対応をすれば、少しでも認知症の方の介護がしやすくなるでしょう。