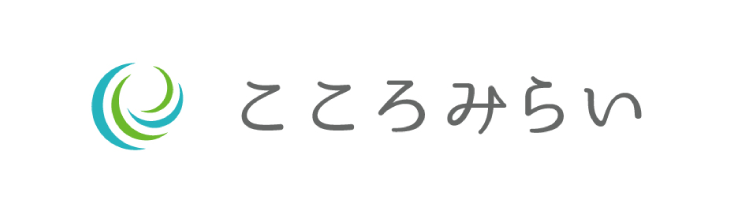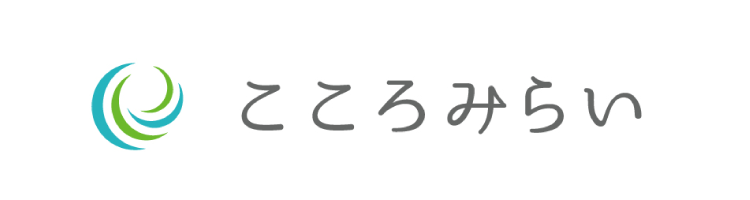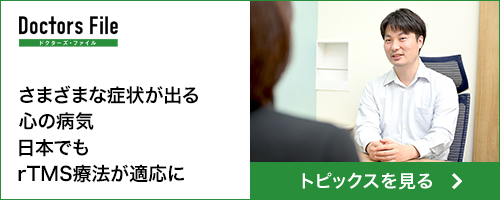元住吉駅前こころみクリニック
〒211-0025
神奈川県川崎市中原区木月1-22-1
元住吉プラザビル 2階/3階
東急東横線・目黒線元住吉駅西口より
徒歩1分
- 内科
- 小児科
- 耳鼻咽喉科
- 婦人科
- 発熱外来
武蔵小杉こころみクリニック
〒211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1
セントア武蔵小杉A棟203
JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分
- 内科
- 心療内科
武蔵小杉こころみクリニック
神奈川TMSルーム
〒211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1
セントア武蔵小杉A棟203
JR線・東急線 武蔵小杉駅より徒歩2分
- TMS
ベルスリープクリニック武蔵小杉
〒211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町3-20-1
光ビル20 7階
JR線・東急線 武蔵小杉駅から徒歩4分
- 精神科
- 睡眠外来
こころみベース
〒211-0025
神奈川県川崎市中原区木月1-28-5
メディカルプラザD元住吉 3階
東急東横線・目黒線 元住吉駅から徒歩3分
- リワーク
- 訪問
- イベント